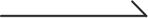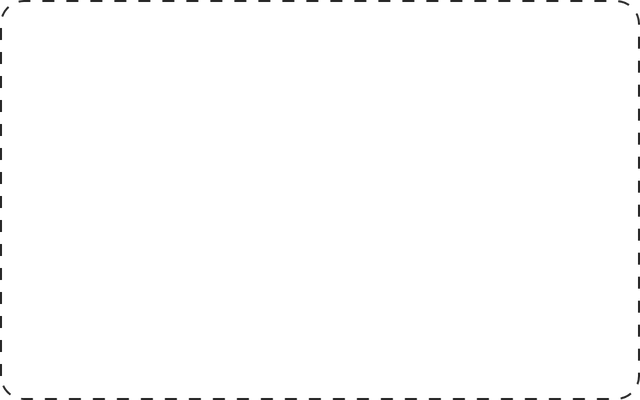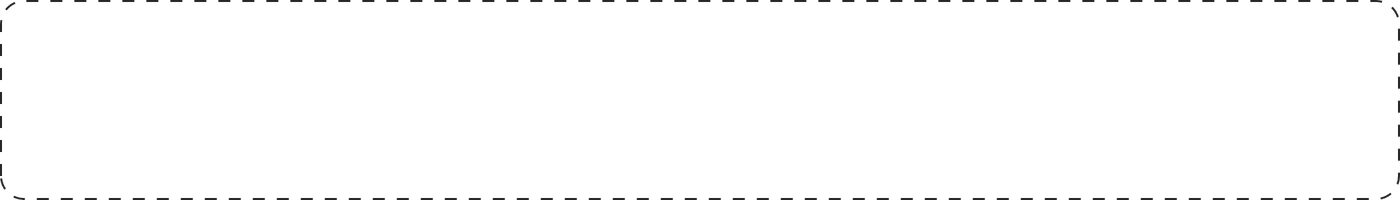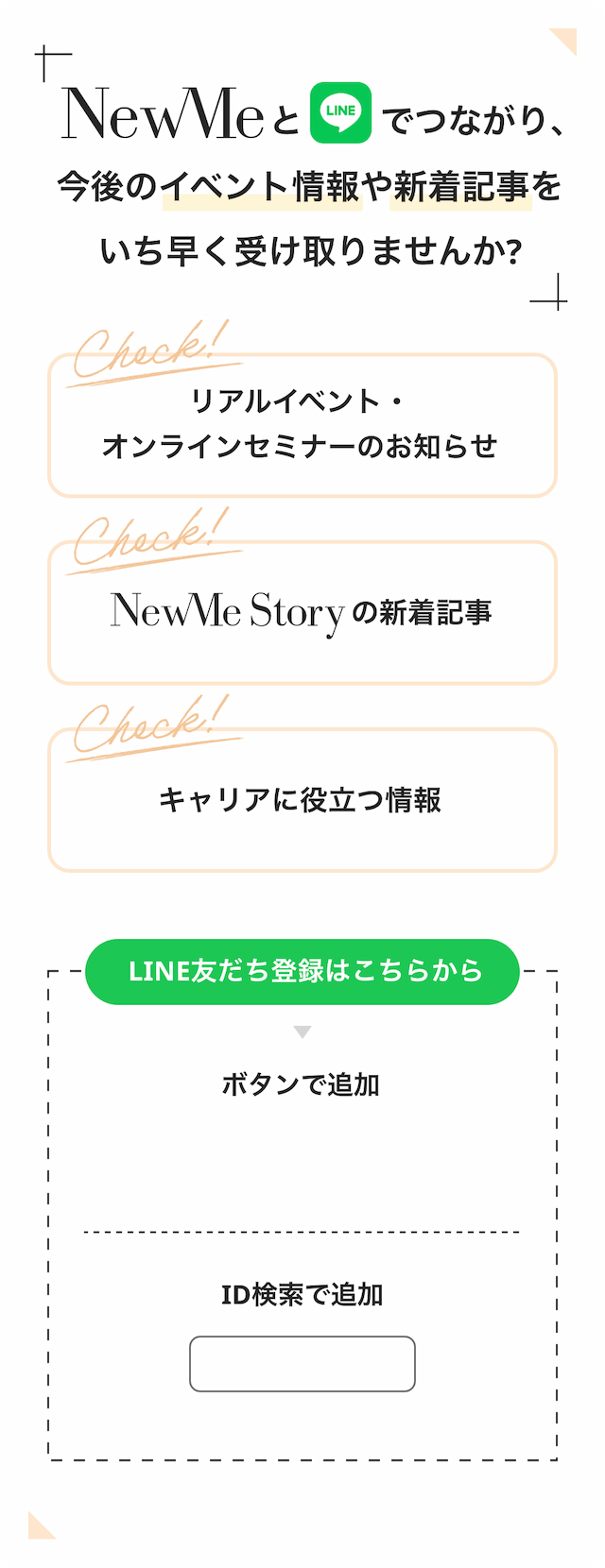【登壇者プロフィール】
石倉 秀明(モデレーター)
公益財団法人 山田進太郎D&I財団 COO
2005年にリクルートでキャリアをスタートし、3社を経て2016年よりキャスター取締役。東証グロース市場へ上場後、2024年2月より現職。現在は、STEM、IT分野のジェンダーギャップ解消に取り組んでいる。
田中 夏代
株式会社博報堂テクノロジーズ データコンシェルジュ担当
大手銀行にて情報系システムのPJ推進に従事。結婚・出産で一度退職するも、約10年のブランクを乗り越え、ベンチャー企業2社を経て、金融系戦略子会社でデータマネジメント業務に辿り着く。2024年10月、博報堂テクノロジーズにデータコンシェルジュとして入社し、グループ横断のデータ活用に注力。
萩原 美緒
株式会社GENDA HRBPマネージャー兼CCO付インナーコミュニケーション担当
クックパッド入社後、1人目人事に。テックカンパニーとしてのブランディングやエンジニア採用に寄与。海外事業・子会社の新規事業立ち上げののち、子どもむけ食品を展開する会社の創業や、10Xで開発部付HRBPとして従事。2023年10月、GENDAにテックチーム専任HRBPとして入社。翌年より全社のインナーコミュニケーション担当を兼任。
藤原 淳子
日本マイクロソフト株式会社 ディレクター
Microsoft R&Dで製品開発に従事し、多様な製品をリリース後、データビジュアリゼーション企業やGitHubで、日本初のソリューションアーキテクトとして従事。ワークショップやコンサルティングを通じて、技術の共有や育成を推進中。業務外では、ハッカソンやメンタリング活動を通じ、女性エンジニアのサポートにも注力。
【イベントレポート】
石倉: 皆さん、こんにちは。本日は「未経験の挑戦も増える【女性×エンジニア】新時代のキャリアの可能性を考える」というテーマで、約45分間お話をしていきます。
日本では理系に進む女性、特にエンジニアになる女性の割合は依然として低い状況です。そのため、実際に活躍している女性エンジニアがいるにもかかわらず、キャリアのロールモデルとして表に出る機会が少ないのが現状です。本セッションでは、女性がエンジニアとして働く上での実際の経験や、キャリアの可能性について深掘りしていきます。それでは、まず登壇者の皆様、自己紹介をお願いします。

田中:博報堂テクノロジーズの田中と申します。私はもともと大手金融機関で情報システム系のプロジェクト推進に携わり、初めてエンジニアという道を選びました。
結婚を機に一度退職し、約10年ほどのブランクを経て仕事に復帰しました。現在はデータマネジメントの仕事を担当し、データコンシェルジュ業務とグループ横断データカタログの整備を行っています。エンジニアと言えばプログラマーのイメージが強いかもしれませんが、私はコミュニケーション力を活かしながらしながら業務に取り組んでいます。今日はよろしくお願いします。
萩原:皆さん、初めまして。株式会社GENDAでHRBPマネージャーを務めております萩原と申します。(2025年2月現在は人事部副部長)GENDAはエンタメ系の企業で、ゲームセンター事業や映画配給など幅広く展開しています。
私のキャリアのスタートはクックパッド株式会社で、エンジニア採用や組織づくりに携わってきました。その後、子供向けの食品会社を起業し、現在は株式会社GENDAで人事を担当しています。私自身はエンジニアではありませんが、長年エンジニアと一緒に働いてきた経験から、今日のセッションでも皆さんに役立つお話ができればと思います。
藤原:藤原と申します。私は外資系ソフトウェア会社で製品開発を経験後、転職を数回経てから戻る「出戻りエンジニア」です。
ソフトウェア製品開発に携わった後、データビジュアライゼーションの会社やGitHubにて日本のプロフェショナルサービス部門を設立し、世界を視野に入れつつ日本のお客様をサポートする役職についていました。よろしくお願いします。
_1XJymd.jpg)
石倉:早速ですが、エンジニア業界における男女比についてお話ししたいと思います。
2023年度の統計では、エンジニアのうち女性は23%と言われています。これについて、皆さんの実感はいかがですか?
田中:現職では女性の多い部門もありますが、部門により女性比率は異なる印象が強いです。私が配属される部門は現職・前職共にエンジニアの女性は少ない印象です。
萩原:近年増えてきたとは思いつつ、数字を聞くとまだ少ないんだなと感じますね。
石倉:また、エンジニアとして管理職に就いている女性は8%と、さらに少なくなります。
ジェンダーギャップの要因として、職場文化や長時間労働の問題、家庭内の役割分担の影響が指摘されています。女性が育休後に重要なプロジェクトから外されるケースもあり、こうした課題がキャリアの進展を妨げているのが現状です。

石倉:まずは、皆さんがエンジニアを目指したきっかけを教えてください。田中さん、いかがですか?
田中:私は数学が得意だったことから理系に進学しました。当時、就職氷河期の影響もあり周囲からは「数学を学んで将来何をやるの?」と言われる時代でした。そんな中で、これからFintechが注目されるだろうと思い、金融機関に就職しました。学生時代から人とコミュニケーションを取ることが好きだったので、理系×コミュニケーション力を活かしてエンジニア系社員と業務系社員の橋渡しを担う役割としてキャリアをスタートしました。
藤原:私は父がハードウェアエンジニアだった影響で、幼いころからプログラミングに触れ、80年代にはラジオでコードが流れ、それをカセットに録音して実行するなんてこともやっていました。その後、中学で父の仕事の関係でアメリカに移住し、プログラミングは知ってるけど英語は分からない状況でしたが、コードには英単語が含まれるためなんとなく会話ができてなんとか生活していました。帰国後、理系に進むことを選び、就職ではハードウェア業界の女性採用はチャレンジングでしたのでソフトウェアのエンジニアの道に進みました。家族からの「これからは男女平等になる時代になる。そのステージに上がれるよう頑張れ。」という言葉を胸にエンジニアとして30年間働いています。
石倉:萩原さんは人事の立場から、エンジニアの採用状況の変化を感じることはありますか?
萩原:はい。これは男女問わず言えることですが、私が初めてエンジニア採用を始めた2008年頃は大学でプログラミングを学んだ人がエンジニアを目指すことが一般的でしたが、近年は独学でエンジニアリングを学び、仕事に就く人が増えてきたなと感じています。企業側も実務経験を重視するものの、それ以前の学び方にはあまりこだわらず、独学でもOKという風潮が広がってきたなと思います。
石倉:確かに、プログラミングスクールやオンライン学習の普及によって、学習環境が整ってきましたね。

石倉:では、エンジニアとして働く魅力について伺いたいと思います。田中さん、どうでしょうか?
田中:AIやテクノロジーは驚くほどのスピードで進化しており、「答えが一つではない」という点が魅力的だと感じています。そのため、男女問わず、さまざまな業務経験がエンジニアの仕事にも活かせる時代になっていると思います。
私自身、復職後すぐにエンジニアとして戻ったわけではなく、まずはスタートアップでできることを限られた時間の中でやりながら、少しずつステップアップしていきました。これまでの経験がすべて線としてつながっていくことが、私にとって醍醐味だなと思っています。
藤原:エンジニアは単に物を作るだけでなく、コミュニケーションを通じて形にし、最終的に誰かが利用してくれることに喜びを感じる楽しい仕事です。成功も失敗もフィードバックの一つであり、結果が見えることに大きなやりがいを感じます。また、スキルを身に着けていればどこでも挑戦できることもエンジニアの魅力だと思います。
萩原:私は人事の視点から「エンジニアは市場価値が高い」という点が魅力だと感じます。企業側は常に優秀なエンジニアを求めており、採用が難しい職種の一つです。また、給与水準も高く、キャリアパスの自由度が高いのも特徴ですね。リモートワークが進んでいる企業も多く、柔軟な働き方ができる点もメリットだと思います。
石倉:確かに、リモートワークやフレキシブルな働き方は、エンジニアにとって大きな利点ですね。一方で、女性エンジニアとして働く上での課題もあると思います。そのあたりについてお聞かせください。

石倉:女性エンジニアの比率がまだ低い中で、働く上での困難や課題を感じたことはありますか?
田中:私の場合、家事・子育てとの両立の中で「時間的制約」です。子供が成長してもまだまだ時間の使い方には工夫が必要です。限られた時間の中で目の前の仕事に丁寧に取り組むことを心がけつつ、周囲としっかりコミュニケーションを取り、自分の状況を理解してもらうことも大切にしています。
藤原:私はこれまでのキャリアの中で、女性であることを理由にハードルを感じたことも過去にはありました。家族の理解があったので、「女性でもどんどん前に出ればいい」と背中を押してくれました。そして、シアトルで勤務していた際は「ロールモデルがいないなら、自分がなればいい」と開き直るきっかけをあたえてもらいました。このままエンジニアとして一生突き進むつもりです。
萩原:弊社にも女性エンジニアがいますが、エンジニア以外のテック系職種(PdMやデザイナー)を含めると、女性の割合は結構高いです。GENDAはゲームセンターのイメージが強いかもしれませんが、映画配給のGAGAや、ポップコーンブランドのヒルバレーなど、エンタメ系のグループ企業が多く、ToC向けのサービスが中心です。そのため、女性の視点を活かしたサービス開発が求められる環境が整っていて女性でいることの利点の方が大きいと感じています。
働き方もフルリモート・フルフレックスで、給与の男女差もありません。サポートする立場から見ても、特に「女性が働きにくい」と感じる場面は少ないですね。

石倉:もし今日このセッションを聞いて「エンジニアになりたい」と思った方がいた場合、何から始めればいいと思いますか?
田中:まず行動することが大切です。悩むよりも、一歩踏み出してみましょう。例えば、エンジニアの中でも「コミュニケーションが得意な人が向いている職種」を選ぶことで、技術力に自信がなくても挑戦しやすくなると思います。
藤原:プログラミング言語はどんどん移り変わるため、何十年後にその言語を使えてもそれが大きな強みになるとは限りません。変わらないのは日本語や英語。日本は人口減少が進んでいて、これから海外の人とのコミュニケーションがますます増えると思われるので、英語はできて損はありません。英語を学ぶことで世界が広がりますし、AIを活用するにも、結局は日本語や英語といった「自然言語」での理解が必要になります。エンジニアに限らず、まずは言葉のスキルを磨くのも大切だと思います。
石倉:最後に、これからのキャリアを考える皆さんへメッセージをお願いします。
田中:今の仕事をしっかりこなしながら、将来を見据えて考えることが大切だと思います。もしエンジニアを目指しているなら、「今の仕事がどうエンジニアとしてのキャリアにつながるか?」を意識して行動することで、自然と道が開けてくるはずです。そうして女性エンジニアとして活躍する人が増えたら嬉しいです。ありがとうございました!
萩原:本日はありがとうございました。私は人事の立場ですが、石倉さんがおっしゃっていたように、エンジニアは需要が高く、機会も多く、比較的高い水準の給与を維持しながら続けられる、とても魅力的な仕事だと思っています。
実際に多くの方が挑戦しているのを見てきましたし、もし興味がある方がいれば、ぜひ一歩踏み出してほしいですね。ここから新たなエンジニアが生まれたら、とても嬉しいです!
藤原:ありがとうございました。世の中のすべての物事は、結局エンジニアリングにつながっていると思うんです。「私は文系だからエンジニアは無理」とかではなく、なにごとにも興味を持って、機会があればぜひ挑戦してみてほしいですね。エンジニアって本当に面白い仕事だと思います。
石倉:皆さん、貴重なお話をありがとうございました。本日のセッションが、皆さんのキャリアの参考になれば幸いです。
\この記事を読んで、一歩踏み出したいと思った方は、こちらからNewMe Jobsにご相談ください/